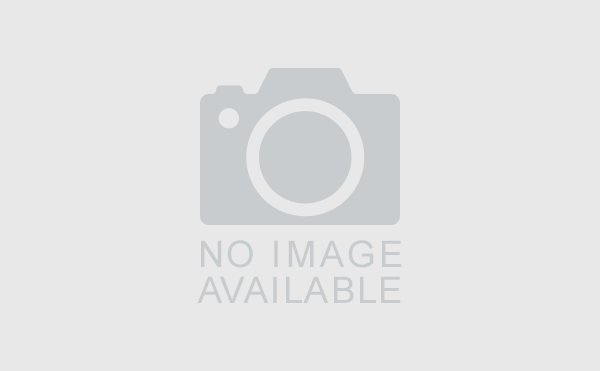【コラム】生前贈与と遺産分割
生前贈与を受けた相続人の扱い
身近な方が亡くなり、相続人が複数いる場合、故人が遺言を残していない限り、不動産や預金などの財産を分けるために遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は、相続人同士が話し合って合意する必要があります。
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行い、それでも合意に至らなければ、最終的には裁判官による審判で決めることになります。
ここまでは、すでにご存じの方も多いかと思います。
今回は、生前贈与を受けた相続人がいる場合の遺産分割協議について、知っておくと役に立つポイントをご紹介します。
生前贈与とは?
「生前贈与」とは、その名のとおり、故人が亡くなる前に、誰かに対して財産を贈与することをいいます。
この生前贈与を受けた人が相続人だった場合、遺産分割の場面では、その贈与された財産を特別受益として相続財産に加えて計算することになります。
これを生前贈与の持ち戻しといいます。
持ち戻しの具体例
少しわかりにくいので、具体的な例で説明しましょう。
Aさんが亡くなり、相続人は長男Bさんと次男Cさんの2人だけだったとします。
Aさんの死亡時点での財産は、500万円相当の土地と500万円の預金、合計1,000万円だったとしましょう。
生前贈与がなかった場合、Aさんの財産はBさんとCさんで2分の1ずつ相続することになり、それぞれ500万円ずつを相続する権利があります(民法900条1項、同条4項)。
ところが、もしBさんが生前に、Aさんから1,000万円相当の土地の贈与を受けていたとしたらどうでしょうか。

Cさんの立場からすると、「Bさんがすでに1,000万円を受け取っているのに、さらに500万円を相続するのは不公平だ」と感じるのも無理はありません。
そのため、法律ではこのようなケースで贈与を受けた財産を“相続財産に戻す”ことで、相続人間の公平を図ります。これが「生前贈与の持ち戻し」という考え方です。
計算の仕方
このケースでは、Aさんの死亡時点の財産1,000万円に、生前にBさんが受け取った1,000万円の土地を加えて、相続財産を2,000万円と見なします(これを「みなし相続財産」といいます)。
法定相続分に従えば、BさんもCさんも1,000万円ずつ受け取る権利があります。
しかし、Bさんはすでに生前に1,000万円分をもらっているので、相続時点で新たに受け取れる財産は0円ということになります。

つまり、CさんがAさんの死亡時に残っていた1,000万円の財産をすべて受け取ることになるというのが、公平な相続ということになるのです。
持ち戻しを知っているかどうかで大きな差が
このように、「生前贈与の持ち戻し」という考え方を知っているかどうかで、相続の結論は大きく変わってきます。
法律上は、相続人の中に生前贈与を受けた人がいる場合、単純に現在残されている財産を分けるだけでは不公平になるという前提で計算されるのです。
ただし、遺産分割協議は話し合いで自由に決めることができるため、たとえ特定の相続人にとって不利な内容であっても、全員の合意があれば有効とされます。
ですから、相続が発生した際に備えて、こうした知識を持っておくことはとても重要です。
持ち戻しを避ける方法もある?
ちなみに、今回の例では、生前贈与を受けたBさんは「相続時点では何ももらえない」という結果になりましたが、実は生前贈与の持ち戻しを防ぐ方法も存在します。
その方法については、また次の機会に解説いたします。