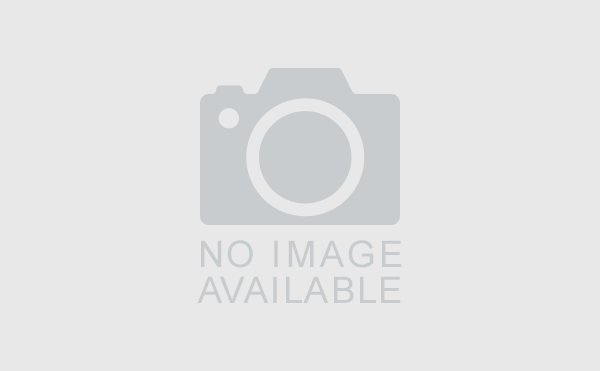【コラム】相続の現場から -遺言の落とし穴-
遺言は、ご自身の築き上げた大切な財産を、ご自身の意思に基づいて残された方々へ引き継ぐための重要な法的文書です。
しかし、その作成には民法で定められた厳格なルールがあり、これを知らずに作成すると、せっかくの遺言が無効となり、ご自身の想いが実現できないばかりか、かえって相続人間に混乱やトラブルを招くことも少なくありません。
このコラムでは、なぜ遺言が必要なのか、そして実際の相続の現場でよく見られる「遺言の落とし穴」を、最新の判例や根拠となる条文を交えながら具体的なエピソードとともにご紹介し、無効リスクを避けるためのポイントを解説します。

遺言はなぜ必要か?
遺言の必要性は、被相続人(財産を残す人)と相続人(財産を受け取る人)双方の視点から理解できます。
被相続人の視点
遺言は、「自分の財産を、誰に・どのように分けるか」という最終意思を形にする唯一の手段です。
たとえば、「長年介護をしてくれた子どもに多めに財産を残したい」「家業を継ぐ人に事業用資産を集中させたい」といった具体的な希望がある場合、遺言を作成しなければ、これらの想いを法的に実現することは極めて困難です。
遺言があることで、ご自身の意思を確実に反映させ、残されるご家族への配慮を示すことができます。
相続人の視点
遺言があれば、相続人全員での遺産分割の話し合いである遺産分割協議の手間やトラブルを大幅に減らすことができます。
特に、家族構成が複雑な場合や、遠方に住む相続人がいる場合など、遺言があることで手続きがスムーズに進み、相続人全員の精神的・時間的負担を軽減することにも繋がります。
なぜ遺言に厳格な方式が求められるのか
遺言は、本人の死後に初めて効力を発揮する特殊な文書です。作成した本人が亡くなった後では、その内容を確認したり、訂正したりすることができません。そのため、以下の目的から民法で厳格な作成方法(方式)が定められています。
- 本人の真意を正確に反映する:
後から「本人の意思ではなかった」と争いになることを防ぎます。 - 偽造・変造を防ぐ:
遺言の内容が勝手に書き換えられることを防ぎ、公正性を保ちます。 - 相続人間の紛争を予防する:
不明瞭な点や疑義が生じないようにすることで、相続人間での無用な争いを未然に防ぎます。
遺言の種類と最低限の形式的要件
遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ最低限の形式的要件が定められています。

| 種類 | 主な要件 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります(認印可)。 なお、財産目録については、パソコンでの作成やコピーの添付も認められています。 ただし、目録にも署名・押印が必要です。 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成する遺言です。 遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。 作成時には証人2人の立会いが必要です。 公証役場で原本が保管されるため、紛失や偽造の心配が少なく、形式不備で無効になるリスクが最も低い遺言です。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言書を封筒に入れて封をして(密封)、遺言書に押印した印鑑で封印します。 その上で、公証人と証人2人の前で、ご自身の遺言書である旨を伝え、それぞれの署名・押印を受けることで、その遺言書が存在することを公的に証明するものです。 遺言書の内容は秘密にできますが、内容の有効性については公証人が関与しないため、形式的な不備で無効になるリスクがあります。 |
【関連記事】自筆証書遺言の書き方とひな形|沖縄の相続に強い弁護士が解説
【関連記事】公正証書遺言の書き方とひな型|沖縄の相続に強い弁護士が解説
遺言の落とし穴
その1 日付
日付の記載は、遺言がいつ作成され、その時点での遺言者の意思能力の有無や、複数の遺言が存在する場合の優先順位を判断する上で非常に重要です。
ケース1:誤記
Fさんは、実際の作成日と異なる日付を自筆証書遺言に記載してしまいました。
相続人の一部が「日付が違うから無効だ」と主張しましたが、最高裁は「日付の誤記があっても、遺言が成立した日が遺言書本体の記載から明確に判断でき、遺言者の真意が確認できる場合には無効とすべきではない」と判断しました(最判令和3年1月18日)。
しかし、後のトラブルを避けるためにも、正確な日付を記載することが最も重要です。
ケース2:「令和六年7月吉日」と記載
Gさんは「令和六年7月吉日」とだけ書いた自筆証書遺言を残しました。しかし、遺言書の日付は「年月日」まで特定できる必要があります。
「吉日」では具体的な日が特定できないため、最高裁は「吉日」などの記載では日付の要件を満たさず、遺言は無効と判断しています(最判昭和54年5月31日)。
日付に関するポイント
- 日付の誤記があっても、他の記載から作成日が明確であれば有効となる可能性がある。
- ただし、後のトラブルを避けるためには正確な日付を記載することが重要。
- 日付は「年月日」まで明記しなければならず、「吉日」などは無効。
その2 封筒や封印
ケース1:自筆証書遺言の場合
Hさんは自筆証書遺言を作成しましたが、封筒に入れずに机の引き出しに保管していました。
相続人は「封筒に入っていないから無効では?」と疑いましたが、自筆証書遺言の場合、封筒や封印は法律上の要件ではありません(民法968条)。
また、封筒に入れても封をしていなくても、自筆証書遺言としての効力には影響しません。
ただし、遺言書を汚損や紛失から守るため、封筒に入れて保管することをお勧めします。
ケース2:秘密証書遺言の場合
Iさんは秘密証書遺言を作成しましたが、封筒に入れただけで封をしていませんでした。
秘密証書遺言は、封筒に入れて「封をし」、さらに遺言書に押印した印鑑で封印しなければなりません。
封をしていない、あるいは封印がない場合は無効となります(民法970条、弁護士会公式解説)。
封筒や封印に関するポイント
- 自筆証書遺言は封筒に入れなくても、また封をしなくても有効。
- 自筆証書遺言でも、汚損・紛失防止のため封筒での保管が望ましい。
- 秘密証書遺言は、必ず封筒に入れて密封し、遺言書に押印した印鑑で封印しなければ無効。
その3 内容が曖昧
遺言は、ご自身の財産をどのように分けたいかを明確に伝えるものです。
内容が曖昧だと、遺言者の真意が分からず、争いの原因となります。
ケース1:「財産を全て任せる」とだけ書いた遺言書
Jさんは「財産を全て任せる」とだけ書いた遺言書を残しました。
誰に何を任せるのか、具体的な分配方法が明記されていなかったため、相続人間で争いに発展。
裁判所は「分割方法が不明確で、遺言としての効力を認められない」と判断しました(最判昭和56年2月17日)。
「すべてを長男に」「残りの財産は孫に」といった書き方でも、誰に何を相続させるかが特定できれば有効とされますが、より具体的な記載がトラブルを避ける上で望ましいです。
曖昧な内容に関するポイント
- 遺言内容は、財産と受取人を明確かつ具体的に記載する必要がある。
- 「すべてを長男に」などでも有効となる場合があるが、トラブル防止には具体的記載が望ましい。

その4 自筆証書遺言で代筆
自筆証書遺言では、遺言者自身の筆跡が真意の証明となります。
ケース1:代筆による自筆証書遺言
Bさんは手が不自由だったため、妻に頼んで代筆してもらい、自分の名前だけ自筆で署名しました。
ところが、相続発生後にこの遺言は「自筆証書遺言の要件を満たさない」として無効と判断されました。
最高裁判所も、財産目録を除き、本人が全文を書いていない遺言は認められないと判断しています(最判昭和43年3月15日)。
自筆でない遺言に関するポイント
- 自筆証書遺言は、財産目録を除き、全文を遺言者本人が手書きする必要がある。
- 一部でも他人が書いた場合は無効になる可能性が高い。
- 身体に不自由がある場合は、公正証書遺言の利用を検討。
その5 押印忘れ
押印も遺言者の真意を確認する重要な要素です。
ケース1:押印のない自筆証書遺言
Cさんは遺言書の本文と日付・氏名を自筆で書きましたが、押印を忘れていました。
相続人の一人が「これは無効だ」と主張し、裁判所も押印がないことを理由に遺言を無効としました(最判昭和53年11月21日)。
押印忘れに関するポイント
- 自筆証書遺言には、必ず遺言者本人の押印が必要。
- 認印でも有効だが、押印を忘れると無効となる。
その6 認知症と遺言能力
遺言作成時に、遺言者が正常な判断能力を有していたかどうかも、遺言の有効性を左右する重要な要素です。
ケース1:認知症の方による遺言
Dさんは高齢で認知症の診断を受けていました。
家族の勧めで公正証書遺言を作成しましたが、後に相続人の一部が「遺言作成時に遺言能力がなかった」と訴訟を起こしました。
医師の診断書や日常生活の状況から、裁判所は「遺言内容を理解できる状態ではなかった」と判断し、遺言は無効となりました(最判昭和57年3月18日)。
認知症と遺言能力に関するポイント
- 遺言作成時に遺言者に意思能力がなければ、どんな形式の遺言でも無効。
- 高齢や体調に不安がある場合は、医師の診断書などで遺言能力を証明する準備が重要。
無効リスクを避けるためのアドバイス
これらのエピソードから学ぶことは、遺言作成には細心の注意が必要だということです。
ご自身の想いを確実に実現するため、以下の点を必ず確認しましょう。
- 日付・署名・押印を確実に記載する: 自筆証書遺言では、この3点が必須要件です。
- 自筆証書遺言は全文自書(財産目録は例外): ご自身の文字で丁寧に書きましょう。
- 内容は「誰に」「何を」明確に記載する: 曖昧な表現は争いの元になります。
- 高齢や体調不良の場合は医師の診断書を取得: 遺言能力があったことの証明になります。
- 不安な場合は公正証書遺言を活用: 公証人が関与するため、形式的な不備で無効になるリスクを大幅に減らせます。
- 秘密証書遺言は「封をして封印」しないと無効になるので要注意:要件を厳密に守りましょう。
まとめ
遺言は「自分の想い」を確実に残されたご家族に伝えるための大切な手段です。
しかし、法律で定められた形式や内容に不備があると、せっかくの意思が実現できなくなるばかりか、かえってご家族間のトラブルの原因となることもあります。
相続の現場では、今回ご紹介したような「落とし穴」が実際に多く発生しています。
大切な財産とご家族のために、遺言作成は法律の専門家(弁護士や司法書士など)に相談し、万全の準備をしましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、ご自身の意思を法的に有効な形で残し、安心して未来を託すことができるでしょう。
参考判例・根拠条文
- 日付の誤記がある遺言書の効力:最判令和3年1月18日
- 「吉日」など特定できない日付の遺言書の効力:最判昭和54年5月31日
- 曖昧な内容の遺言書の効力:最判昭和56年2月17日
- 自筆でない遺言書の効力:最判昭和43年3月15日
- 押印のない遺言書の効力:最判昭和53年11月21日
- 遺言能力が問題となった事例:最判昭和57年3月18日
- 自筆証書遺言の形式:民法968条
- 秘密証書遺言の封印要件:民法970条
 |
この記事を書いた弁護士 弁護士法人ニライ総合法律事務所 代表弁護士 古賀 尚子 |